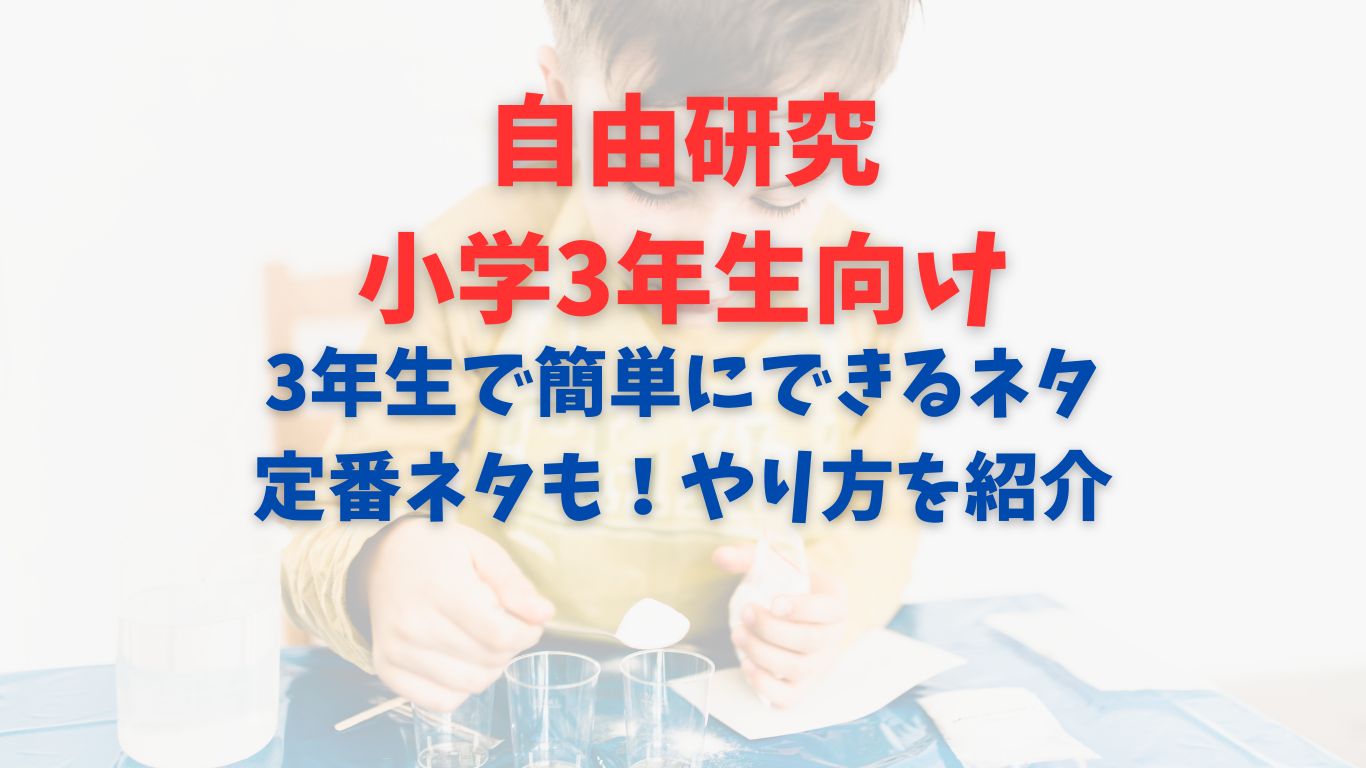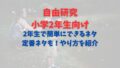夏休みの宿題といえば、自由研究。
小学3年生の自由研究は、化学反応、化学変化を利用したり、生物系の自由研究ネタを選ぶ子どもも増えてきます。
今回は、夏休みの自由研究で小学3年生が簡単にできる化学反応、化学変化を利用したもの、生物系の自由研究ネタを紹介していきます。
夏休みの自由研究・小学3年生の簡単な観察系ネタ
夏休みの自由研究で、小学3年生ができる観察系ネタをいくつか紹介していきます。
氷が解ける部屋と時間と温度を調べる
自分の家の中で一番早く、氷が解ける部屋と時間と温度を調べるというもの。
用意するもの
- 氷(冷蔵庫の製氷機1箱)10個ぐらい 氷は実験の度、一つずつ冷蔵庫から取り出す。
- 洗面器
- 温度計
- ストップウォッチ
実験内容
- 自分の部屋の各場所で、冷蔵庫の冷凍室から氷を1つずつ取り出す。
- 洗面器に氷を入れて、温度計を置き、ストップウォッチを動かす。
- 氷が解けた時間と温度をまとめて集計する。
- 集計した内容をまとめて発表資料にする。
カビの研究
色々なお店のパンを購入する。
町の手作りパン屋さん、スーパーで売っているヤマザキ、パスコ、フジパンなど、さまざまなメーカーのパンを選ぶ。
また、食パン、クロワッサン、甘いパン、しょっぱいパンなど、パンの種類もいろいろ揃えてみる。
それぞれ同じ条件で放置していくと面白い結果が出るはず。
どのパンがどの程度でカビ発生し、どこまで広がっていくかのスピード含めて、観察すると楽しい。
指紋の違いを調べてみよう
ガラスコップに付いた指紋に、アイシャドウの粉をふりかけ、刷毛などで丁寧に余分な粉を落とす。
指紋型に残った粉をテープにうつし、黒い紙に貼る。
これを家族分作って、家族や兄弟でも指紋が違うというのを調べるというもの。
ゴーヤーのツルの巻き方調べ
次の3点について数えて顕著な差があるのかを調べるというもの。
- ゴーヤーのツルが1本の苗から何本出ているか?
- ツルが巻く向き(右巻き、左巻き)はどちらが多いか?
- 途中で回転の向きが変わるが、巻く回数は一定なのか?
鉢植えだけではデータとして少ないので、苗を使って自宅で育てたゴーヤで観察するといいでしょう。
支柱などがない空中では、ツルが巻く径はほぼ一定、4回巻いたら逆回転など、150本以上のツルを観察すると興味深いことがわかるかもしれません。
左右の向きに顕著な差は見られるのでしょうか…
観察の様子を撮影、図、空中でただ巻いているだけの長さの比較、数えたものの表を作成するなどすればかなり本格的な自由研究になりますよ。
さまざまな卵の殻が解けていく様子を観察する
生卵を殻ごとお酢にひたし、生卵の殻が溶けてすけすけぷよぷよになるのを観察する実験。
生卵、ウズラの卵、ゆで卵などを使って、実験を行い、その違いを確かめるというもの。
どれくらい殻がきれいに溶けるか、期間はどの程度かかるかなど。
また、すけすけになった卵を割って、どのようになるかの検証を行なう。
生卵はきれいにすけすけぷよぷよになるものの、他の卵はそこまで綺麗にはならないケースが多いとか。
夏休みの自由研究・小学3年生の簡単な実験系ネタ
続いて、小学3年生が面白いと感じる簡単な実験系ネタを紹介します。
コーラは本当に骨を溶かすのか?
コーラを頻繁に飲むと骨が溶けて脆く弱くなる、という噂は本当なのかを実験するもの。
実験に使うために用意するのは、チキンの骨。
チキンの骨をコーラに漬けておき、日々経過観察を行い、その結果をまとめていくというもの。
噂のように、コーラは本当に骨を溶かすのか?を検証する。
ドライアイスで炭酸しゅわしゅわスイーツ
ドライアイスを発泡スチロールに敷き詰めて、その上にしゅわしゅわにしたいフルーツを並べます。
スイカやオレンジなどは、カットしてから入れるといいです。
蓋をして数時間放置したらしゅわしゅわ食感のフルーツが完成です。
低学年でもできるない内容ですが、ドライアイスの取り扱いに注意が必要なので中学年程度がよいかと思います。
フルーツ以外にも豆腐とか、水分が多いものならできます。
時間によって、しゅわしゅわ感の違いがどれだけでるかや、どの食べ物ならしゅわしゅわするかなど、比較しながら実験をすれば、よりしっかりとした自由研究になりますよ。
まとめ
3年生になると、いよいよ身近な自然現象や化学反応に触れるような自由研究ネタを選ぶ子どもも増えてきます。
まだまだ、お子さんひとりですべてやるというのは大変でしょうから、将来的にも理科に興味が持てるように、身近な大人がしっかりサポートをしてあげるといいでしょう。