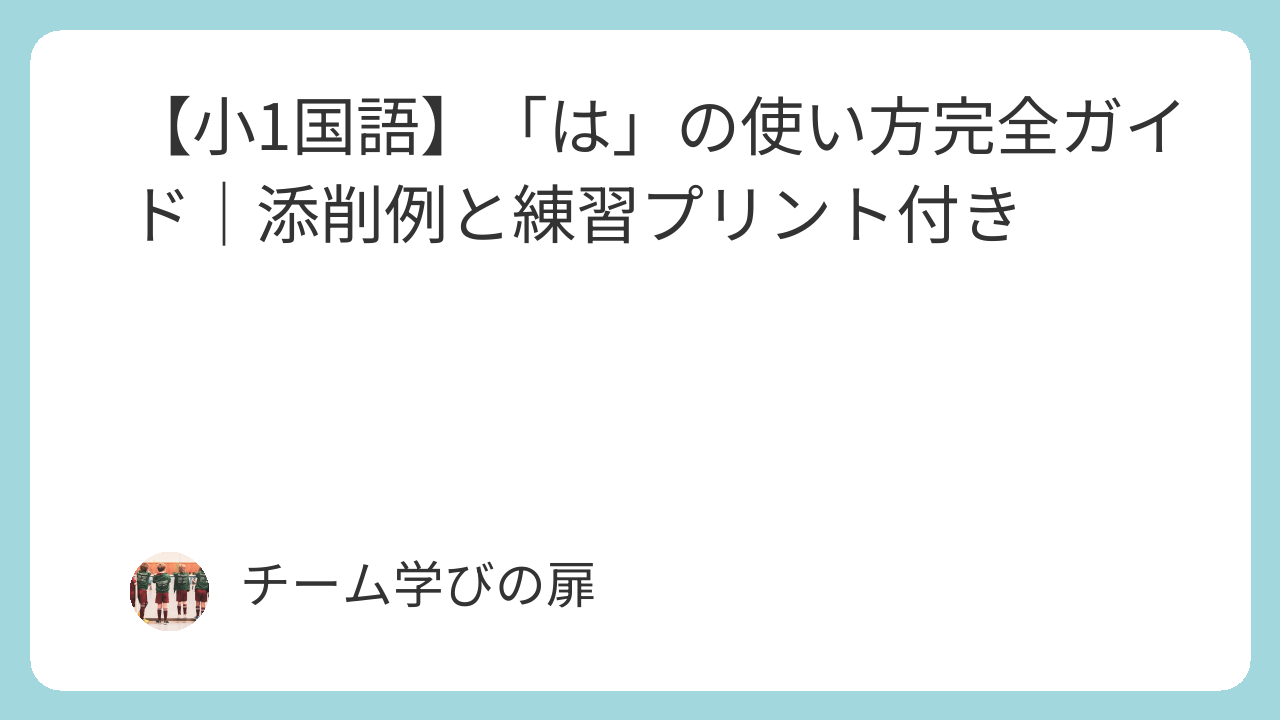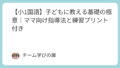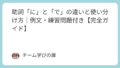こんな悩みはありませんか?
□ お子さんの作文で「は」の使い方が不自然
□ 「は」を使った文章の添削方法がわからない
□ 家庭での効果的な練習方法に困っている
この記事では、そんな悩みを持つママに向けて
□ 助詞「は」の基本的な使い方をわかりやすく解説
□ 実際の作文の添削例と具体的な直し方
□ すぐに使える練習プリントと指導方法
をご紹介します。

助詞で迷ったときは、いつでもこちらから全体を確認できます😊
→ 助詞の使い分けまとめページを見る
助詞「は」の基本
小学1年生にとって助詞「は」は、文章を書く上で最も基本となる重要な要素です。
ここでは、「は」の基本的な役割と具体的な使い方について、お子さまが理解しやすい例文とともに解説していきます。
「は」の基本的な役割
助詞「は」は文章の中で「これから話題にすること」を示す働きをします。
文の主役を明確にし、読み手に「何について話すのか」を伝える大切な役割があります。
- 文の主題を示す(例:「ぞうは大きいです」)
- すでに知っていることを表す(例:「あのねこは白いです」)
- 比較や対比を表現する(例:「わたしは公園が好きです」)
- 説明の対象を明確にする(例:「そらは青いです」)
- 文章の主役を示す(例:「はるは暖かいです」)
これらの基本的な使い方を意識することで、自然な文章表現が可能になります。
日常会話の中でも、「は」の使い方に注目してみましょう。
「は」を使った基本例文
お子さまが普段使う言葉や身近な場面を例にして、「は」の使い方を具体的に見ていきましょう。
実際の使用場面に即した例文を通じて、正しい使い方を学んでいきます。
基本的な例文
- わたしは1年生です
- そらは青いです
- ねこは寝ています
- りんごは赤いです
- うさぎは耳が長いです
これらの例文を参考に、お子さまと一緒に「は」を使った文作りを楽しんでみましょう。
身近な題材から始めることで、自然に使い方を覚えることができます。
作文の添削例と直し方
お子さまの作文での「は」の使い方について、具体的な添削例をご紹介します。
よくある間違いとその直し方を知ることで、効果的な指導が可能になります。
実際の作文例を見ながら、添削のポイントを確認していきましょう。
よくある間違いパターンと添削例
作文指導では、「は」の使い方に関する典型的な間違いパターンがあります。
これらの間違いを理解し、適切な直し方を知ることで、効果的な指導が可能になります。
添削のポイント
- 「は」の重複使用を避ける
- 「が」との使い分けを明確にする
- 主語と述語の関係を整える
- 文のつながりを自然にする
- 適切な場面での「は」の使用
添削する際は、お子さまの気持ちに配慮しながら、一つずつ丁寧に説明することが大切です。
正しい例を示しながら、わかりやすく解説していきましょう。
効果的な添削のポイント
お子さまの作文を添削する際は、やる気を失わせないような配慮が必要です。
まずは良い点を見つけて褒め、その上で改善点を優しく指導していきましょう。
添削時の重要ポイント
- 良いところを先に褒める
- 一度に直しすぎない
- 具体例を示して説明する
- お子さまの表現意図を確認する
- 書き直す機会を設ける
添削は学習の機会であり、失敗を責めるものではありません。
お子さまが自信を持って文章を書けるよう、温かい励ましを忘れずに指導しましょう。
練習プリントと指導方法
「は」の使い方を楽しく学べる練習プリントをご用意しました。
イラストを使った基本問題から、実践的な応用問題まで、お子さまのレベルに合わせて段階的に学習を進めることができます。
基本の練習プリント
まずは、「は」の基本的な使い方を確認する練習からスタートします。
イラストを見ながら答える形式なので、お子さまも楽しく取り組むことができます。
練習問題1:基本の「は」
イラストを見て( )に「は」を入れよう
- ぞう( )おおきいです
- ふうせん( )あかいです
- いぬ( )はしっています
- おひさま( )まるいです
練習問題2:「好きです」「できます」
好きなものや、できることを「は」を使って書こう
- わたし( )えほんが好きです
- ぼく( )およぐことができます
- おとうと( )バナナが好きです
- おねえちゃん( )ピアノができます
練習問題3:見つけたことを書こう
窓の外で見つけたものを「は」を使って書いてみよう
- とり( )とんでいます
- はな( )さいています
- くも( )しろいです
- そら( )あおいです
応用練習問題1:文を作ろう
次のことについて、「は」を使って文を作りましょう
- あなたの好きな動物
- 今日の天気
- 家族のこと
- 学校でのできごと
応用練習問題2:間違いを直そう
次の文を正しく直してみましょう
- ぼくはサッカーは好きです
- ねこはいぬは友だちです
- うさぎは耳は長いです
- きょうは晴れは気持ちいいです
応用練習問題3:日記を書こう
「は」を使って、今日あったことを3文で書いてみましょう
(例)
きょうは公園に行きました。
すべりだいは新しくなっていました。
お友だちは元気でした。
これらの練習問題は、基本から応用まで段階的に学習できる構成になっています。
お子さまの理解度に合わせて、適切な問題を選んで取り組んでいただけます。
練習方法と上達のコツ
日常生活の中で自然に「は」の使い方を学べる工夫をご紹介します。
楽しみながら学べる活動を通じて、正しい使い方が身につくようサポートしていきましょう。
日常生活での練習方法
普段の会話や読書の中で、自然に「は」の使い方を学ぶことができます。
特別な時間を設けなくても、日常的な場面で練習の機会を見つけることができます。
実践のポイント
- 絵本読み聞かせでの活用
- 親子での会話での意識づけ
- 日記指導での実践
- テレビ番組の活用
- ゲーム感覚での練習
無理なく継続できる方法を選び、楽しみながら学習を進めることが大切です。
お子さまの興味や生活リズムに合わせて取り入れていきましょう。
おすすめ教材
効果的な学習のために、おすすめの教材として「小学1年生「は・を・へ」のつかいかた (くもんのにがてたいじドリル こくご 1)」をご紹介します。
家庭学習に適した教材を選ぶことで、より効率的な学習が可能になります。

「小学1年生「は・を・へ」のつかいかた (くもんのにがてたいじドリル こくご 1)」の主な特徴
- 学習のねらいと効果
- つまずきやすいポイントを的確に把握し、理解を深められる
- 「苦手を作らない」「苦手を得意に変える」という段階的な学習が可能
- 自学自習に適した構成
- 学習内容の特徴
- 1冊1単元の集中学習方式
- 易しい内容から段階的に学習できる構成
- つまずきやすい箇所を重点的に復習
- 学習者に優しい設計
- 1ページあたりの学習量を抑えた構成
- 取り組みやすく、達成感を得やすい
- 細かなステップアップ方式により自信をつけやすい
この「小学1年生「は・を・へ」のつかいかた (くもんのにがてたいじドリル こくご 1)」の最大の特長は、苦手意識を持ちやすい助詞「は・を・へ」の使い方を、無理なく段階的に学べる点です。
特に小学1年生の発達段階に配慮した、きめ細かな学習ステップと、自学自習を促す工夫が随所に見られます。
教材選びは、お子さまのレベルと興味に合わせることが重要です。まずは基本的な問題から始めて、徐々にレベルを上げていきましょう。
家庭学習のためのチェックリスト
□ 基本的な「は」の使い方が分かる
□ 短い文が作れる
□ 日記で正しく使える
□ 間違いを自分で直せる
□ 自然な文章が書ける
まとめ
助詞「は」の使い方は、文章作成の基礎となる重要な要素です。
この記事で紹介した方法を参考に、お子さまのペースに合わせて練習を進めていってください。
焦らず、楽しみながら学習を続けることで、確実に力が身についていきます。
日々の会話や読み聞かせの中で、少しずつ正しい使い方を身につけていきましょう。
助詞の使い分けは、一度に覚えようとすると難しいですが、少しずつつなげて学ぶと理解がぐっと深まります😊
気になるところから、ゆっくり確認してみましょう。
助詞全体をまとめて確認したい方はこちら👇
➡助詞の使い分けまとめページへ
おうち学習を、無理なく続けたい方へ
「は」は話題を知らせる助詞なので、声に出して読むことで理解が進みます。
毎日少しずつ繰り返すことで、かならず定着していきます😊
もし、お子さんのペースに合わせて、やさしく基礎から支えてあげたいなと感じたら、
おうちでも取り組める通信教育を活用するのもひとつの方法です。
📖 まずは「じっくり基礎を積みたい」なら
ポピーは、教科書にそった紙教材で、書いて覚える習慣づけがしやすい教材です。
助詞・漢字・読解など、小学生でつまずきやすい基礎の部分を丁寧に支えてくれます。
▶ ポピーの無料おためし見本を取り寄せてみる
👉ポピーの公式サイトへ
🌱 「学習習慣づけもサポートしたい」なら
スマイルゼミは、タブレット1台で学習が完結する通信教育です。
その日にやる内容が自動で出るので、「なにから手をつけたらいいの?」と迷わずに学習がすすめられます。
▶ スマイルゼミの資料請求はこちら
👉スマイルゼミの公式サイトへ
どちらも、まずは「おためし」や「資料請求」からで大丈夫です。
お子さんに合うペースと方法を、ゆっくり見てあげてくださいね☺️